こちらの記事は
| ・一方的に話す人が周囲になぜか集まる人
・自身が一方的に話すことが多く、原因を探りたい ・一方的に話す人のメカニズム、原因、心理について知りたい |

なぜ一方的に話すのかな…どんな原因が?
といった感じで気になっている人がいると思います。
僕自身も十代、二十代の頃は一方的に話す人が周りに多く、よくヘトヘトになっていました。
三十路も半ばを過ぎたくらいから、ようやく一方的に話す人との距離の置き方がわかったのです。
一方的なおしゃべりを続ける人の対応策、対処法なども交えて解説していきます。
他人の弾丸トーク、マシンガントークの押しつけで疲れている人は、ぜひ読んでくださいね!
【参考記事|一方的に話す女性の心理9つ&対処法】

- 一方的に話す人は「会話泥棒」&「時間泥棒」でもある
- 一方的に話す人は損をしている
- 一方的に話す人の心理10個
- 基本編① 傾聴する
- 基本編② 聞いているフリをする
- 基本編③ 話題を変える
- 基本編④ 距離を置く
- 応用編① 制限時間を設ける
- 応用編② 要約を返す
- 応用編③ 役割を変える
- 応用編④ 共感+切り上げフレーズを持つ
- 応用編⑤ 第三者を巻き込む
一方的に話す人は「会話泥棒」&「時間泥棒」でもある
冒頭で書いたとおり、アラフォーの僕が半生を反省したとき、一方的に話す人との関わりがあまりにも多すぎました。
これは僕自身の対人エネルギーの弱さに起因していることもあるのですが、一方的にしゃべる弾丸トーク、マシンガントークの持ち主はどこにでも存在。
その原因がわからないとモヤモヤしますし、わかっても対処法や対応策が見つからないと事態を改善できません。
また一方的に話す人は時間泥棒になるだけでなく、強引に会話のラリー中に主導権を奪取しがちな会話泥棒であることもよくあります。
一方的に話す人は損をしている
「話す」というのは「一方的に喋る」とは違うのだ
— 藤花祭楽過 (@10Srnk) February 27, 2019
まず結論としてお伝えしておきたいのが、一方的に話す人はどんどん損をするということです。
| ・自己中心的な人
・自分に酔っている人 ・相手を尊重できない人 |
と高確率で思われてしまいます。
自業自得といえばそれまでですが、そもそもなぜ彼ら彼女らは一方的に話すのでしょう。
一方的に話す人の心理10個
そもそも「なぜ一方的に話をするのか、わからない」という人が多いのでは?
どうして彼ら彼女らが、一方的なトークを繰り広げる原因がわかると、スッキリしますし、対策を練ることが可能。
では一方的トーカーの心理7つを紹介します!
【参考記事▼】

一方的に話す人、原因その①「発達障害かも?」
著者 栗原泉「ブレない子育て 発達障害の子、『栗原類』を伸ばした母の手記」本日より発売! ー アメブロを更新しました#栗原類#KADOKAWAhttps://t.co/Hp40u8XfiU pic.twitter.com/rGdy6gYw6T
— 栗原 類/Louis Kurihara (@Louis_Kurihara) June 14, 2018
モデルの栗原類さんが、「自分は発達障害であると」発表し話題となりました。
だんだんと「発達障害」というワードが、世間に浸透しつつあります。
何度同じことをやっても身に付かない。人との交流が深く発展しない。自分の感情がコントロールしにくい。すぐに一方的に怒ってしまう。周囲の環境になじめない。不器用。タイムマネジメントができない。記憶力に不安がある。自分には心当たりがないのに上司や家族から責められる……。
注目してもらいたいのは
| ・自分の感情がコントロールしにくい |
という点。
一方的に話す人は、ときに興奮しながらしゃべるものの別に怒っているわけではありません。
彼ら彼女らは自分の感情をコントロールしたくても、できない状態にあるのです。
同じページから引用しましょう。
発達障害が疑われる人の症状はさまざまですが、その主な原因は、脳の中にある海馬の発達の遅れ「海馬回旋遅滞症」にあると考えられます。
海馬回旋遅滞症(かいまかいせんちたいしょう)とは、耳慣れない言葉ですね?
もう少し読み進めていきます。
脳の記憶をつかさどる部位である海馬は、胎児のときから、回転しながら発達しており、右の海馬のほうが、左の海馬よりも少し速く発達することがわかっています。
加藤俊徳博士によれば、記憶を司る部位である海馬はグルグルと回転しながら大きく成長していくとのこと。
大半の人は左右で比較すると、右の海馬がやや大きめになる傾向にあるようです。
左の海馬の発達のスピードが極端に遅れることがあり、この遅れが、さまざまな脳の発達障害や、性格の特徴、コミュニケーション障害などを生み出していると考えられます。
海馬の左右サイズを比べた際に、左側だけが極端に小さいケースが。
左海馬の未発達によって、発達障害が起こるのです。
海馬回旋遅滞症かどうかは、MRIを使い脳画像を可視化することですぐわかるようになりました。
もしご自身が「一方的に話しすぎているかも?」と思われた方は、MRIを使った脳画像診断を受けてみるのもひとつの選択です。
ASDの人は、空気が読めない、とよく言われますが、大人になっても無愛想だったり、コミュニケーションが成り立たなかったりする人もいます。
ADHDの人もコミュニケーションスキルが未熟なため、自分のことで精いっぱいで他者配慮ができない場合があります。
ADHDは多動性障害、ADSは自閉症スペクトラムのこと。
空気が読めなかったり、一方的になる原因は脳の偏りである可能性が考えられます。
一方的に話す人、原因その②「話すことが大好き」
人間にはタイプがあります。話すのが大好きな人もいれば、聞き手に回ることを好む人も。
一方的に話す人の何割かは、おしゃべり依存症です。
誰かに何かを話すだけで、気分が高揚してしかたありません。誰でも有頂天になっていると、相手の気持ちに気づきにくいもの。
この手の人が、人付き合いで選び相手の基準は「自分が心地よく話せるか?」です。
凹凸が噛み合えばいいのですが、聞き手に負担を強いているようであればマズいですね。
一方的に話す人、原因その③「自分の話が面白いと勘違い」
例え一方的であっても、起伏に富んだ面白いものであれば好まれます。
会う度に
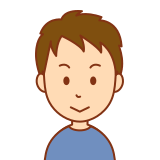
何か面白い話してよ!
と、せがまれこともあるでしょう。
問題はエンタメ的なトークと異なる、ひとりしゃべりをしてしまう人たち。
過去をさかのぼった際に、聞き手の反応に対してとても鈍感な人がいました。
彼があるとき口にした一言に、僕は耳を疑いました。
それは「みんな俺の話で楽しんでくれている」と言ったのです。
残念ながら、彼は一方的に話しすぎるため、あまり他人から好かれていませんでした。
なんて悲しきすれ違い…。サービス精神で良かれと思ってやったことが、マイナス評価を得るとは切ないですね。
一方的に話す人、原因その④「見切り発車トークが習慣化」
会話のやり方は男性と女性で異なります。
あくまでそういう傾向が強いだけの話ですが、男性は結論へ向かってしゃべり、女性はしゃべること自体を楽しむもの。
男性でも女性でも、結論を定めずに見切り発車で話し始める人がいます。
彼ら彼女らのトークは、一方的になりがち。
ゴールが見えていないので、延々と迷走しているイメージです。
結果、時間泥棒になることもよくあります。
見切り発車トーカーは、会話しながら結論を探す
話していて

結局、何が言いたいの?
と思ったことはありませんか?
そのように感じさせるトーカーは、しゃべりながらどこへ向かうか考えます。
『会話のゴール』を共有できていないため、相手は不安と不快感を覚えます。
一方的に話す人、原因その⑤「承認欲求が強い」
聞いてくれるからと行って、
一方的な話し方は相手を尊重できてないよなぁ。そんなのツイッターに書いとけよって話ばっかりだった気がする。
大人はみんな疲れており、時間は有限なのだ。
たぶん、社会的に安定している人に俺は認めてもらいたかったのだろう。
鬱屈した承認欲求には品性がない
— jun (@mukunena) February 11, 2019
承認欲求とは文字通り、「他者から認められたい(承認されたい)願望」です。
彼ら彼女らが人に何かを話す目的。それは非常にはっきりしています。
何かを伝えることで、
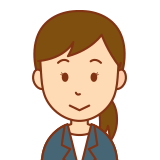
すごいね!!
と、ほめたたえられること。
なぜそういった心理になるかといえば、満たされていないからです。
もし複数の人にしっかり話を聞いてもらえれば、一方的に話す癖が改善されるかもしれません。
一方的に話す人、原因その⑥「自己愛や自己顕示欲が強い」
自己顕示欲や自己愛は、承認欲求とセットで使われることも多い用語。
自分自身の力量や存在を目立たせたり、他人から注目を浴びようとしたりする欲望のこと。字義通りには「自己顕示」をしたいという「欲」という意味になるが、「自己顕示欲」という風に表現する場合は、批判的に使われる場合が多い。
他者に注目されるための自己顕示表現が、一方的なおしゃべりであるということですね。
続いて自己愛に目を移しましょう。
自己愛とはnarcissismの日本語訳であり、自分自身を愛することや大切に思う事を意味している。その意味で 自己愛とは誰にでもある心理であり(Cooper,1986 )人が生きていくために必要なことであろう。 例えば Fromm(1956)は 自分を愛することができない人は他人を愛することもできないと述べている。
ネガティブなニュアンスで使われることも多い自己愛ですが、他者を愛するためにはまず自身を愛せているかが問われます。
近年この自己愛の肥大化が指摘されており(福島1992;小此木1992;町沢1998), 自分の自己愛を守るために平気で他人を傷つけたり利用をするような行動パターンや、あるいは自分自身の自己愛が傷つかないために、自己愛が傷つく可能性のある場面を避け、学校や社会からひきここもるような現象も増えている。
フォーカスしてほしいのは、「自己愛を守るために他者を利用するような行動パターン」の箇所です。
相手を、自分の吐き出したいものの受け手と見なす考えは、「他者を利用する」に該当。
自己愛、自己顕示欲が暴走すると、相手への敬意を忘れて、自己満足なひとりしゃべりに終始することがあります。
また聞き上手な繊細さん、HSPに対して、ついマウントをとり「お前聞く人、俺話す人」という尊大すぎるしゃべり方をする自己愛人間、ナルシストも存在します。
【自己愛を傷つけられた際、尋常じゃない怒り方をする人の記事は▼】

一方的に話す人、原因その⑦「聞き手の反応が悪いため焦ってる」
こちらの項目に該当する人は、自己陶酔するがゆえ視野が狭くなり一方的に話してしまう人とは反対。
むしろ聞き手の反応が見えています。
しかし見えすぎるがゆえに、相手の反応が気になってしかたないケースも。
私自身も感情があまり出ない方なので、たまに話している人から

どう思って聞いているのかよくわからない
と言われることも。
確かに感情表現が豊かな人ほど、聞き手に向いています。
会話はコミュニケーションのため、お互いの感情が行き来し交流できる方が、話す方も乗るもの。
とはいっても性格や感情の出し方は人それぞれ。
どれが正しくて、間違っているなど正否を判定するものではありません。
反応が薄い人と話している人は「楽しんでくれてないから、もっとたくさんしゃべらないと…」と焦りが生まれ、長時間のトークを一方的に展開していることがあります。
これはひとえに情報不足&「〇〇はこうあるべき」という決めつけが原因。
もともとそれほど反応しない人だとわかっていれば焦りませんし、
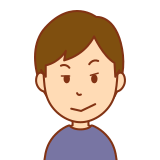
俺のトークを聞けば感情が激しく動くはずだ!
という考えがなければ、そもそも動揺しないでしょう。
自身の話術を過信している、うぬぼれ屋に多い心理です。
一方的に話す人、原因その⑧「老化で前頭葉が萎縮」
前頭葉の機能低下にによって、一方的に話す人となるケースがあります。
まず前頭葉が何に関与しているのか見ていきましょう。
前頭葉
優位半球(通常は左)の前頭葉前半部は、思考、自発性(やる気)、感情、性格、理性などの中心です。病気や怪我で優位半球の前頭葉が障害されると、これらの機能が低下します。具体的には、几帳面な人がだらしなくなったり、幼稚になったり、極端な例ですと目はあけているけど一日中ぼーっとしてなにもしない状態になります。
成熟している人が会話中に己を抑制できるのに対し、精神的に幼い人は自身のコントロールが苦手。
自分が言いたいことをただ話すなど、コミュニケーションが一方的になりやすいのです。
お年寄りの脳機能が低下していくのは理解の範疇かもしれません。
しかし早い人なら、四十路あたりから前頭葉の働きが悪くなるというのです。
長らく精神科医として勤務してきた和田秀樹さんの言葉を引用します。
40代以降の「脳」について知っておく
①前頭葉の萎縮……早い人で40代から縮み始める、つまり老化し始めます。萎縮が 進むと、感情のコントロールがきかなくなったり、思考が平板になったりします。
多くの人が想像しているよりも、私たちの脳は老い始めます。
もしあなたの周囲で、最近

突然、会話が一方的になったなあ…
と思う人がいたら、前頭葉の機能が低下している可能性があるでしょう。
一方的に話す人、原因その⑨「コミュニケーションがとれないタイプのオタク」
まず初めに断っておきますが、オタクの人全員が一方的に話をして、コミュニケーションがとれないわけではありません。
オタクの何がダメかって自分の話したいことだけ一方的に話すばかりで人の話は全く聞こうとしない事だわ。
— みーあきゃっと (@XveORpcVuiES04O) November 27, 2019
一部のオタクの人達は、他者の気持ちを想像するのが苦手。興味の有無がかなりの凹凸になっているようです。
目の前にいる人が興味のない話をし始めても、合わせることを一切しないのに、自分の話したい話題になると、会話の主導権を強奪し、一方的に話すオタクが中にはいるのだとか。
相手の話を聞く気がないのに、自分の話を聞いてほしいというスタンスでは、もちろん好かれづらいのは確か。
自己中心的な人と思われても、しかたありません。
話をひたすらキャッチさせられる人からすると、「たまにはこちらの話も聞いてほしい…」と思うのは、極めて当然のことでしょう。
一方的に話す人、原因その⑩「愛着障害かも?」
まずは愛着障害が何なのかをお伝えします。
乳幼児期に長期的に虐待やネグレクト(放置)などを受け、子どもの頃に得るはずだった他者、特に養育者に対する安全感・安心感を獲得することができなかったために引き起こされる障害の総称。
幼少期に親が子供へどんな接し方をしたのかは、かなり大切。
親が子供に対して、どんなコミュニケーションをとったかは一生涯に渡って影響を与えます。
その子供が大人になっても「問題が棚上げされたまま」ということがよく起こります。
発達障害と愛着障害はよく似ているため、専門家でも判断に迷うといいます。
愛着障害の症状は、発達障害の症状に似ているため、しばしば混同されることがあります。しかし、発達障害は先天性のもの、愛着障害は後天性のものである、という決定的な違いがあります。
発達障害は先天的に脳の部位に何らかの偏りが見られます。
愛着障害は幼少期の深い傷つきによって、後天的に起こるという違いがあります。
不安型の人は、愛着対象に対する期待がとても大きい。子どものころ、愛着対象から条件付きの不安定な愛情しか与えられなかったことで、愛情に対する飢餓感が強いのだ。
文中の「不安型」というのは、不安型愛着障害を指します。
一方的に話してくる人と仲良くなり、親との関係や家庭環境を尋ねることに。
答える際、彼ら彼女らは悲しい顔をしていました。
異常なルールやこだわりを子供に押しつけ、人格に悪影響を与えてしまう親や、ダブルバインド(二重拘束)によって子供との信頼関係を損ねてしまう親などによって育てられると、健全な愛着が中々得られません。
意図せずにマシンガントークをしてしまう人の多くは、幼少期、親に甘えたかったが甘えられなかった人たちです。
親との適切な距離感があった上で十分な愛情を与えられることは、本当に大切です。
過度な愛着障害は言葉のキャッチボールが不可能になることも…
愛情の飢餓によって、言葉のラリーやキャッチボールができなくなっている人たちをたくさん見てきました。
愛着障害を抱えた人たちは、安心できる相手を見つけると、幼き日にできなかった行動をとります。
みなさんも小学校時代を思い返してください。
学校から帰ると、その日あったことを自分の親へ報告しませんでしたか?
興奮して長話になったこともあったでしょう。
愛情深い親で余裕があれば「うん、うん」と、うなずきながら優しい笑顔で子供の話に耳を傾けます。
愛情に植えている愛着障害の人は、この状況を無意識に再現し、必死に上書き保存の修正作業を続けているのです。
『心の安全基地』を求める愛着障害者たち
安全基地(あんぜんきち、英: Secure Base)とは、アメリカ合衆国の心理学者であるメアリー・エインスワースが1982年に提唱した人間の愛着行動に関する概念である。子供は親との信頼関係によって育まれる『心の安全基地』の存在によって外の世界を探索でき、戻ってきたときには喜んで迎えられると確信することで帰還することができる。
安全基地は、何をしても許される場所。
例え悪いことをしたあとに叱られることがあっても、人格まで否定される心配はありません。
子供時代に「心の安全基地」を確保できなかった人間は、親のように慕える人を必死で探しています。
その過程で一方的に話してしまうことも。
また誰かを親と同一視してから、マシンガンのようにトークすることもあるでしょう。
一方的に話す人への対処法:基本編と応用編
会話の場には、必ずといっていいほど「マシンガントーカー」と呼ばれるタイプの人が存在します。延々と自分の話を続けてしまう人のことです。
もちろん、中には意図的に相手を疲れさせようとする人もいるかもしれません。しかし、多くの場合はそうではなく、無自覚にまくしたてるような話し方になってしまっているのです。その背景には「さびしさ」や「承認欲求の強さ」が潜んでいます。
それを理解した上で、私たちはどのように対応すればよいのでしょうか?ここでは、基本編4つ+応用編5つの合計9つの対処法を紹介します。
基本編① 傾聴する
カウンセリングの世界では、クライエントの話を否定せずに聞く「傾聴」が大切だとされています。カール・ロジャースの来談者中心療法はその代表例です。
一方的に話す人の多くは、幼少期から「自分の話を真剣に聞いてもらえなかった」という体験を持っています。だからこそ「今度こそは聞いてほしい」という欲求が強く働くのです。
真剣に耳を傾けるだけで、相手が満たされて落ち着くことは少なくありません。ただし、自分のキャパシティを超えてまで聞き役に徹する必要はありません。聞く側が消耗しすぎれば、関係は長続きしないからです。
基本編② 聞いているフリをする
夢中で話している人は、案外こちらの反応を気にしていないものです。適度に「うんうん」と相槌を打つだけで、相手は「聞いてもらえている」と感じます。
実際には頭の中で別のことを考えていても構いません。これは「自分の心を守る」ための手段でもあります。大切なのは、聞き役である自分をすり減らさないことです。
基本編③ 話題を変える
軽く切り替えの言葉を挟みながら話題を変えるのも有効です。
「そういえば、この前のニュース見た?」
「話は変わるけど、今度一緒に行こうと思ってたカフェがあってね」
相手が柔軟であれば、スムーズに会話の方向が変わります。ただし「会話泥棒」タイプは強引に自分の話に戻してきます。そういう場合は別の手を考えた方がよいでしょう。
基本編④ 距離を置く
どうしても会話が成立しない相手とは、物理的にも心理的にも距離を置くことが最も健全です。
私自身、以前は「話を聞いてあげなければならない」と思い込んでいました。しかし、相手の背景を知っている場合を除き、無理に付き合う必要はありません。
相手の生い立ちや環境を理解しているからこそ関わり続けられる場合もあるでしょう。ですがそれはあくまで例外です。自分の生活や心を守るために距離をとる勇気も必要なのです。
応用編:さらに実践的な5つの方法
ここからは、基本編を踏まえたうえで使える応用編です。状況に応じて柔軟に使い分けると、会話がグッと楽になります。
応用編① 制限時間を設ける
延々と話す人には、時間の枠を与えることが効果的です。
「今から10分なら大丈夫だよ」
「この後予定があるから、それまでに教えてね」
と伝えると、相手も無意識に話をまとめざるを得なくなります。これはカウンセリングや会議でもよく使われる方法です。
応用編② 要約を返す
相手が長々と話している途中で、こちらから「つまりこういうことだよね」と要約して返すのも有効です。
要約には二つの効果があります。
-
「ちゃんと聞いてくれている」と相手が安心する
-
話の脱線を止めて軌道修正できる
延々と迷路のように話す人に対しては、この「要約返し」で出口をつくってあげるのがポイントです。
応用編③ 役割を変える
「たくさん話してくれてありがとう。今度は私の話も少し聞いてもらえる?」と伝えることで、自然に役割交代ができます。
一方的に話す人は「聞き手の気持ち」を体験する機会が少ないため、逆の立場になるとハッとすることがあります。繰り返すうちに、双方向の会話の心地よさを理解してもらえるかもしれません。
応用編④ 共感+切り上げフレーズを持つ
話が長引いたときには、共感を示したうえで切り上げるフレーズを持っておくと便利です。
-
「わかるよ、それ大変やったね。でも続きはまた今度ゆっくり聞かせて」
-
「面白い話だから、次に会ったときの楽しみにするね」
このように相手を否定せずに会話を終えると、関係を壊さずに自分を守れます。
応用編⑤ 第三者を巻き込む
グループでの会話なら「〇〇さんはどう思う?」と話題を振って、聞き役を分散させましょう。
一対一で抱え込むと疲れてしまいますが、第三者を巻き込むことで、相手も「自分の話が広がった」と満足しやすくなります。
まとめ
一方的に話す人は、必ずしも悪意からそうしているわけではなく、さびしさや承認欲求が背景にあるケースが多いものです。
-
基本編:傾聴/聞き流す/話題転換/距離を置く
-
応用編:制限時間/要約返し/役割交代/共感フレーズ/第三者を巻き込む
これらを状況に応じて組み合わせれば、会話の負担を減らしつつ、相手との関係性も守れます。
大切なのは、自分の心身を守りながら相手に向き合うことです。聞きすぎて疲れたら、離れることも選択肢。関係性は一方通行でなく、互いの余白があってこそ続いていくものなのです。



コメント